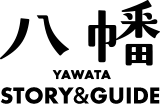正法寺
- 本堂
- 大方丈 上段の間
徳迎山・正法寺は、男山丘陵の南東にある古刹です。建久2年(1191)、源頼朝の幣礼使として、清水(現.静岡県静岡市清水区)からこの地にやってきた鎌倉幕府御家人・高田蔵人(くろうど)忠国が、天台宗の寺を開いたことに始まります。3代目の宗久(そうきゅう)が出身地の清水に因んで「志水(しみず)」と改姓し、寺は志水氏の菩提寺となりました。天文15年(1546)からは、後奈良天皇(1497~1557)の命で勅願寺となり発展し、この頃浄土宗に改宗されました。現在まで江戸時代前期の寺院建築がよく保存されており、仏像、絵画など数々の有形文化財を所蔵し、名勝庭園も見どころとなっています。
江戸時代のはじめ、志水家の娘であるお亀の方(1576~1642)が伏見城に住んでいた徳川家康公(1543~1616)の目に留まり、側室となりました。地元に伝わる話では、子どもを行水させていたところに家康公の大名行列が通りかかり、子どもごとたらいを持ち上げるのを見て、家康公はお亀の方に目を留めたともいわれています。お亀の方は家康公の第9子、尾張徳川家初代となる義直(よしなお)公(1600~1650)を産んだため、お亀の方の菩提寺となった正法寺は、尾張藩の厚い庇護を受け発展しました。
本堂、大方丈、唐門は寛永7年(1630)にお亀の方の寄進で建てられ、国の重要文化財に指定されています。本堂の本尊は観音・勢至の両菩薩を従える阿弥陀如来坐像で、鎌倉時代の作と推定されており京都府暫定登録有形文化財となっています。お亀の方や徳川家の位牌も祀られている本堂内陣は、日光東照宮の内陣を手がけた絵師による約400年前の彩色がそのまま残っており、当時を偲ばせる鮮やかな色彩を見ることができます。本堂の軒先には全国で唯一正法寺にしかない「逆輪(さかわ)」という金に輝く飾りが見られます。地垂木、飛檐(ひえん)垂木の先端に取り付けられるのは通常金具ですが、ここでは木製の箱状の飾りに金箔を貼っており、木が造り出す柔らかな表情がお亀さんを偲ばせます。
大方丈には、松の大木などを描いた雄大な襖絵が飾られており、上段の間に描かれた煌びやかな大障壁画である琴棋(きんき)書画図は、狩野派の絵師によるものと推測されています。京都府指定文化財である小方丈および書院から望む庭園は京都府指定名勝です。他にも彫刻や古文書など豊富な文化財があり、唐門に掲げられた山号「徳迎山(とっこうざん)」、本堂正面の寺号「正法寺」の扁額は後奈良天皇の宸筆によるものです。境内の法雲殿には、南へ約一キロメートルのところにある八角堂にかつて祀られていた巨大な阿弥陀如来坐像が安置されています。
通常非公開ですが、決まった公開日に拝観できます。

木造 阿弥陀如来坐像
正法寺境内の法雲殿には、全長約4.8メートルの巨大な阿弥陀如来坐像が祀られています。結跏趺坐(けっかふざ)し、穏やかな表情で、両手は胸の前で中品中生(ちゅうぼんちゅうしょう)の説法印を結んでいます。鎌倉時代の作で、国の重要文化財に指定されています。
像自体の高さは約2.8メートル、檜材で、かつては漆に金箔で覆われていました。高さ約4.8メートルにもなる光背には13体の化仏を配し、金箔が今なおわずかに残っています。作者の銘はなく、その様式から鎌倉時代に活躍した仏師・快慶(かいけい)の作品ではないかと推測されています。
この像は、石清水八幡宮がかつて神仏習合の宮寺であった頃から残された貴重な仏像です。もとは石清水八幡宮本社近くにあった八角堂に祀られていました。八角堂は、鎌倉時代はじめの建保年中(1213~1219)に、順徳天皇の発願により建てられた隅切り八角形の仏堂で、阿弥陀如来坐像もこの頃造られたものと考えられます。
明治元年(1868)、政府は神仏分離令を発し、石清水八幡宮の境内から仏堂や仏像が撤去されることとなりました。八角堂が失われることを惜しんだ正法寺住職、志水円阿は、八角堂と阿弥陀如来坐像を譲り受け、明治3年(1870)に正法寺近くの西車塚古墳の後円部墳頂に移設しました。その後、阿弥陀如来坐像は京都国立博物館に寄託されていましたが、平成20年(2008)に正法寺境内の法雲殿に移されました。