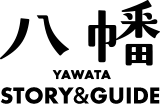善法律寺
- 善法律寺 表門
- 紅葉の境内
善法律寺は、男山の東麓にある律宗の仏教寺院です。秋には境内にある約100本の紅葉が大変美しいことから、「もみじ寺」とも呼ばれています。秋だけでなく、春にも鮮やかな新緑が境内を彩ります。
鎌倉時代の正嘉年間(1257~1259)、当時は神仏習合の宮寺であった石清水八幡宮の検校(けんぎょう)を務めた善法寺宮清(ぜんぽうじきゅうせい、または、みやきよ)(1225~1276)が自身の邸宅を寄進し、善法寺家の菩提寺として建立されました。室町時代、善法寺家は足利将軍家との関係が特に深く、宮清の曾孫である紀
良子(きの
よしこ)(1336~1413)は、室町幕府2代将軍である足利義詮(よしあきら)の側室となり、3代将軍となる義満(よしみつ)を産みました。このため歴代の足利将軍は何代にもわたり善法律寺を参詣し支援しました。境内の紅葉は、良子が寄進したものであるといわれています。
本堂は寛永16年(1639)頃、表門は宝暦9年(1756)に建てられており、京都府指定文化財です。
本堂は五間四方の建物で、石清水八幡宮の旧社殿の材を使って建てられたと伝わります。内陣の高御座(たかみくら)に祀られる本尊の八幡大菩薩像は平安時代の作で、地蔵菩薩像であった可能性があり、後年、八幡大菩薩として信仰されるようになったといわれています。かつては石清水八幡宮に祀られていましたが、明治元年(1868)の明治政府による神仏分離令を受け、善法律寺に移されました。堂内の両脇に祀られている大きな不動明王像と愛染明王像は、鎌倉時代の作です。奥殿の阿弥陀堂には本尊として宝冠阿弥陀如来像(市指定文化財)が祀られています。この像も石清水八幡宮境内にあったもので、山下の頓宮にあった極楽寺から移されたと伝わります。
境内には、石清水八幡宮の神宮寺で現在の石清水八幡宮駅前ロータリー辺りにあった大乗院(だいじょういん)から移されたという五輪塔があり、石清水八幡宮大西坊(たいせいぼう、または、おおにしぼう)の僧侶で忠臣蔵で有名な大石内蔵助の養子として赤穂浪士の討ち入りを助けた覚運(かくうん)の墓塔などがあります。
境内の散策は自由ですが、本堂の拝観は事前予約が必要です。