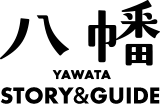神應寺
 本堂
本堂
京阪電車
石清水八幡宮駅から男山を見上げると、中腹に見える堂舎が絲杉山・神應寺です。石清水八幡宮とは谷をひとつ隔てた北の峰の頂部に伽藍を構えます。駅前から徒歩3分で山門に至り、その先には驚くような渓谷が目の前に現れます。境内は春のシャガや初夏のアジサイなど季節の花のほか、紅葉の名所として知られており、春の青もみじに加え、秋には緑から黄、赤と徐々に色づく紅葉の美しいグラデーションが長い期間楽しめます。さらにはイギリスで改良された桜・アーコレードが、春と秋に花を咲かせるようになっており、紅葉と桜を同時に見ることもできます。
貞観元年(859)、奈良大安寺の僧・行教が宇佐より八幡大神を男山に勧請し、その翌年の貞観2年に八幡宮社殿が造営され、これに伴い神應寺も創建されたと伝わります。八幡大神は第15代天皇として数えられる応神天皇が神格化された存在であり、応神天皇の位牌所として始め応神寺と称しましたが、天皇の諱(いみな)を憚って神應寺に改めたといいます。
はじめ法相宗であった宗旨は、天台宗、次いで真言宗と長い歴史のうちに変わりましたが、室町時代の応永15年(1408)に曹洞宗となりました。第12代住職の弓葴善僵(きゅうしんぜんきょう)は豊臣秀吉と同郷の尾張出身で親交も厚く、秀吉の正室・北政所が深く帰依したこともあり寺は発展しました。江戸時代には徳川家康に続き、5代将軍の徳川綱吉からも厚く崇拝されました。
本堂には、本尊の薬師三尊仏のほか、豊臣秀吉の子・秀頼からの寄進ともいわれる衣冠束帯の豊臣秀吉像や、国の重要文化財に指定されている行教律師の像も祀られています。行教律師坐像は平安時代前期の作で、江戸時代まで石清水八幡宮三ノ鳥居近くにあった開山堂に安置されていたものが、明治元年(1868)からの明治政府による神仏分離令で廃仏毀釈のため取り除かれ、明治6年(1873)に神應寺本堂に移されました。
神應寺の谷の奥には「奥の院」があり、杉山谷不動尊には不動明王や市指定文化財である矜羯羅(こんがら)童子・制多迦童子像が祀られています。秘仏として大切に祀られてきた大聖不動明王は、古来より広く信仰を集めてきました。さらに奥には「ひきめの滝」があり、神仏に祈願する滝行が今も行われています。
神應寺の奥の院を含む境内は自由に散策できますが、本堂拝観には事前予約が必要です。