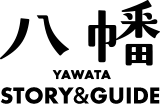飛行神社

飛行神社は、日本で初めて動力飛行機を発明した二宮忠八(1866~1936)によって大正4年(1915)に創建されました。安全な空の旅を祈願する場所として有名であり、世界は同じ空の下でつながっているという信念により、国籍関係なく航空事故で亡くなったすべての人々の霊を祀っています。
忠八は、愛媛県八幡浜市の出身で、両親亡き後、伯父の薬種商で働いていた10代の頃、独創的で奇抜な凧を設計して販売し、「忠八凧」として評判となりました。看護卒を務めていた20代の頃には、カラスが滑空する姿から着想を得て、固定翼のゴム動力による「カラス型飛行器」を製作し、25歳となった明治24年(1891)に飛行を成功させました。明治26年(1893)には、尾翼がなく人が乗ることができる複葉機モデルの「玉虫型飛行器」を設計しましたが、資金不足のため断念しました。彼は製薬業界で数年働いた後、明治34年(1901)八幡の地に移り、実物大の試作機の製作を開始しました。しかし、完成前の明治36年(1903)にライト兄弟が動力付き重航空機の持続飛行を世界で初めて成功させました。
これを受け、忠八は製作を断念したものの、航空への熱意を失うことはありませんでした。飛行機の時代に入ると、飛行機関連の事故による死者が増えたことを悼み、大正4年(1915)に自邸内に私財を投じて飛行神社を創建しました。飛行神社の本殿は3つの祭壇からなります。本殿中央には、空の神様である饒速日命(にぎはやひのみこと)を祀り、向かって左側は日本薬学界の偉人らを祀る薬光神社、向かって右側は航空事故で亡くなられた航空殉難者と航空業界の先覚者を祀る祖霊社です。
現在の拝殿は平成元年(1989)に古代西洋風に再建され、円柱と、発明のきっかけとなった烏を描いたステンドグラスの装飾が特徴的です。併設の資料館には、忠八が撮影した写真や自筆の資料、本人が晩年に作り残した玉虫型飛行器(模型)をはじめ、発明に関連する品々などが展示されており、航空愛好家から寄贈された何百もの飛行機模型も展示されています。