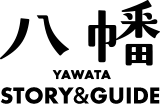相槌神社

相槌神社は、石清水八幡宮の参道の入口にあり、八幡五水として知られた井戸・山ノ井のそばに建てられた、刀剣に関係の深い神社です。神社に伝わる伝承や江戸時代の記録によると、平安時代に活躍した有名な刀鍛冶、大原五郎太夫安綱(やすつな)が、山ノ井の水を使って刀を鍛造したとき、神が来て「相槌(あいづち)」をなす、すなわち交互に槌を打ち合わしたため、ここに神を祀ったといいます。その刀は、源氏一族に伝えられてきた名刀、髭切と膝丸であったとも伝わります。
江戸時代には「合槌稲荷社」と呼ばれており、今も祭壇の両脇には、2体のキツネの像が並んでいます。別名、藤木井とも呼ばれた山ノ井は、元禄9年(1675)に石製の井筒などが寄進されて整備され、八幡五水のなかでは唯一、今も豊富な水が湧き生活に使われています。神社の銘板には、いつの頃か不明ですが、平安時代の著名な刀工・三条小鍛冶宗近の名も加えられました。江戸時代中期、宝永7年(1710)頃までは石清水八幡宮の管理下にありましたが、その神徳への信仰が非常に強かったことから、その後の時代は近隣住民が独自に神社の修繕を行ってきたことが、幕末の地誌『男山考古録』に書かれています。
謎の多い刀剣である髭切と膝丸は、来歴に諸説あり、長い歴史の中でその名称と所有者が何度か変わっていることがわかっています。現在は、京都の北野天満宮と大覚寺にそれぞれ保管されている2本の刀が、伝説の髭切と膝丸ではないかと考えられています。これらの刀は重要文化財に指定されています。
相槌神社は参拝自由です。毎月1日、15日の月次祭では東へ徒歩約12分の春日神社(京都府八幡市八幡西1)で御朱印の授与などが行われています。詳しくは、相槌神社公式サイトをご覧ください。