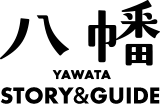伊佐家住宅
 主屋
主屋
伊佐家住宅は、村の長である庄屋を代々務めた伊佐家に受け継がれている、江戸時代中期の山城地方の代表的民家です。
昭和50年(1975)に、主屋と棟札が国の重要文化財に指定され、昭和55年(1980)に5つの蔵、木小屋、普請文書、古図、宅地が追加指定されました。
江戸時代を通じ、徳川幕府の領地である「天領」の管理を担うとともに、村の長を務めた庄屋の邸宅たる堂々とした造りとなっています。
享保19年(1734)に再建された主屋は、茅葺の屋根の厚さが特徴的で、玄関から座敷に見られる、当時伏見の桃山から出土した「桃山」という土で塗られた赤い壁や、祭祀用の大きな「くど」は、家の格式の高さを示しています。主屋の南側には、かつて賓客を迎えるために使われていた、正面玄関に続く木製の式台が備えられています。このような式台は身分の高い家にしか許されておらず、家の格式を表しています。賓客は式台から玄関の間へ入り、仏間を経て奥座敷に入りました。奥座敷には手の込んだ欄間彫刻があり、床間と違棚を備えた書院造で、飾り棚の引き戸は金箔を用いた絵で飾られています。玄関の間と控えの間、そして奥座敷は全て、江戸時代の姿のまま今日まで伝えられており、伊佐家が日常的に使っていた道具の多くも良い状態で保存され、今なお家中で見ることができます。蔵は表に長蔵、裏に内蔵、更にその裏に東蔵、木小屋、二階蔵、乾蔵が石垣の上に立ち並び、主屋から乾蔵までは高縁(こうえん)という渡り廊下で結ばれています。
敷地は約2600平方メートルあり、周囲には石垣が築かれ、かつて屋敷を囲んでいた堀の跡が南側にあり、また北側には竹林があります。
伊佐家住宅は一般公開されていませんが、予約制で見学することができます。