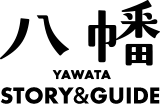松花堂庭園・美術館MAP

 松花堂庭園
松花堂庭園
美しい景観を誇る松花堂(しょうかどう)庭園は、歴史的な建造物や茶室を受け継ぎ、美術館を併設した八幡市の施設です。松花堂庭園は約20,000平方メートルの広さがあり、「内園」と「外園」で構成されています。40種類以上の竹、約300本の椿のほか、梅や桜、紫陽花、もみじなどがある広々とした庭園では、一年を通して、四季を感じることができます。また、園路をゆったりと歩き、茶室を眺めたり、池の錦鯉に餌をあげたり、水琴窟の透明感のある音を聴きながら、静かな雰囲気を楽しんでいただけます。
 紅葉の松花堂庭園
紅葉の松花堂庭園
この庭園の名前は、石清水八幡宮の社僧・松花堂昭乗(しょうじょう)(1584~1639)に由来しています。昭乗は、かつて神仏習合の宮寺として宗教と文化の中心であった石清水八幡宮に仕えており、男山の山腹にあった僧坊「瀧本坊」の住職でした。一方、江戸時代初期を代表する文化人として知られ、茶の湯、書・絵画などを得意とし、特に書においては、「寛永の三筆」のひとりとされています。
内園には、昭乗が隠居後に住んだ「泉坊」に江戸時代まであった草庵「松花堂」(京都府指定文化財)と、書院(京都府登録文化財)が移築されており、国の史跡・名勝に指定されています。
内園を囲む外園には、趣きの異なる本格的な茶室3棟があります。小堀遠州ゆかりの「閑雲軒」を復元した小間がある「松隠」、千宗旦好みの小間がある「梅隠」、竹を露地に取り込んだ四畳半の「竹隠」はそれぞれ特色があり、これらの建物を含む庭園の保存と文化の継承を図るため、昭和52年(1977)に八幡市が資料館を設置し、庭園を一般に公開しました。
茶会や文化イベントが定期的に開催されています。平成14年(2002)に開館した松花堂美術館では、草庵「松花堂」や泉坊書院に付属する内装品、松花堂昭乗に関連する茶道具類、そして八幡市にゆかりのある美術品等を収蔵するとともに、展覧会を開催して歴史・文化・観光情報を発信しています。