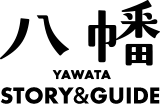石清水八幡宮 本社
- 手前から楼門・舞殿・幣殿・本殿(外殿・内殿)
- 織田信長公寄進「黄金の雨樋」
- 欄間彫刻(蟷螂)
- 目貫きの猿
石清水八幡宮の本社は、国内で現存する最大かつ最古の八幡造(はちまんづくり)の神社建築であり、本社を構成する10棟の建造物と棟札3枚が国宝に指定されています。現在の本社は徳川3代将軍である徳川家光公の下で本殿・武内社・楼門・廻廊が修造の対象とされ、寛永11年(1634)に完成しました。
石清水八幡宮は、時の権力者から崇敬を集めていたため、戦国時代の天下人がこぞって寄進を行いました。織田信長公は天正8年(1580)、八幡造の大屋根の間に懸かる「黄金の雨樋」を寄進し、豊臣秀吉公は天正17年(1589)に本社廻廊を再興しており、その子である秀頼公は慶長11年(1606)に本社の造替を行ったと伝わっています。「黄金の雨樋」が今なお健在であることに加え、年輪年代の調査から瑞籬(みずがき)欄間(らんま)の材などに慶長期の造営物が含まれていると指摘されており、天下人の度重なる修造が今の本社の基礎となっているといえます。初代徳川将軍の徳川家康公は、本社の修造は行っていませんが、八幡領の検地を免除し石清水八幡宮の保護を図りました。
正面の楼門(ろうもん)からつながる丹塗の廻廊は、神社建築として類例の少ない大規模なもので、その中の建物主要部は朱漆塗です。楼門の屋根から奥に連なって見える舞殿(ぶでん)、幣殿(へいでん)は本殿と同じく檜皮(ひわだ)葺で、廻廊と東西両門が本瓦葺であるのと対照的です。神楽(かぐら)を奉納する舞殿が楼門・幣殿と空間として一体化している構成は、他に見られない特徴であるといわれています。
本殿は、国宝である宇佐神宮本殿とともに、八幡(はちまん)造を代表するものとなっています。切妻造りの建物が前後に並んだ形式で、前の外殿と奥の内殿は中でつながっており、この二つの屋根の間に「黄金の雨樋(あまどい)」が懸けられています。前後の殿が横に三つ連なっており、中央に応神天皇、向かって左に比咩(ひめ)大神、右に神功(じんぐう)皇后が祀られていて、外殿が居間、内殿が寝所であるといわれています。
本殿を囲む瑞籬(みずがき)をはじめとする欄間(らんま)や、外殿や門の蟇股(かえるまた)など随所に150点余り施された極彩色の彫刻は、当代最上級のものであり、華麗な四季の草花と鳥獣の取り合わせが美しく、麒麟(きりん)、犀(さい)や蟷螂(かまきり)といった珍しい題材や、西門の「目貫きの猿」が見どころです。伝説の名工といわれる左(ひだり)甚五郎がつくった猿に魂が宿り、夜間抜け出して山麓の畑を荒らすため、猿の右目に竹釘を打ち付け閉じ込めたという逸話が残っています。
石清水八幡宮では、通常は御祈祷される方しか入ることができない社殿内部を、お祓い・参拝ののち神職がご案内する「昇殿参拝」が行われています。詳しくは石清水八幡宮のホームページでご確認ください。