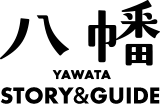石清水八幡宮の末社と摂社
 本社と摂社・末社
本社と摂社・末社
織田信長公が寄進したと伝わる築地塀(信長塀)に囲まれた石清水八幡宮の本社の周りには、摂社や末社に位置付けられる社があります。本社に祀られる八幡大神に所縁の深い神を祀った大小の社殿があり、一か所で日本各地の神に参拝できるようになっています。
北東にある若宮社および若宮殿社の歴史は古く、本殿から遅れること70年程、平安時代前期のうちには創建されていました。現在の両社殿は寛永年間(1624~1644)頃の建築で、国の重要文化財となっており、若宮社は珍しい日吉(ひえ)造です。本殿での祈祷ののち「清め衣」に願いを書き、男性は若宮社、女性は若宮殿社に奉納します。
他の社も鎌倉時代までには数多く建っており、そのようすは古絵図から知ることができます。多くは戦国時代頃に一旦失われましたが、北東の水若宮(みずわかみや)社と、北西の住吉社は、江戸時代前期に再興されました。寛永頃の建築で、国の重要文化財に指定されています。その他の社、東から気比社、貴船社・龍田社、一童社、廣田社・生田社・長田社は、江戸時代末に建てられました。
北西隅の校倉(あぜくら)(宝蔵)は、江戸時代中期からある類例の少ない校倉建築で京都府指定文化財です。