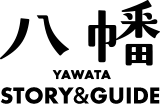石清水八幡宮 五輪塔(航海記念塔)

石清水八幡宮の一ノ鳥居の外側を、神應寺の山門へ向かう小道の北側に、巨大な五輪塔があります。その様式から鎌倉時代(12世紀末~1333)に建てられたと推測されており、高さ6メートル、最下段の横幅は2.4メートルあり、中世以前の五輪塔では日本最大で、国の重要文化財に指定されています。
五輪塔は仏塔の一種であり、平安時代中期に日本で建てられはじめました。ほとんどの場合石造りで、形は物質構成の5つの要素を象徴しており、下から順に、「地、水、火、風、空」を表します。この石塔より小さな五輪塔の多くは、墓標や記念塔として寺院などで江戸時代を通して数多く建てられ、年紀があるものもよく見られます。
一方、この石塔には刻銘がなく、制作者や年代、目的など不明で、謎が多い五輪塔です。この石塔についての言い伝えは複数あり、有力な説では、平安時代末頃、日宋貿易の摂津尼ケ崎の商人が中国から帰国する途中、海上で嵐に巻き込まれ、あわや転覆かの時、石清水八幡宮に一心に祈ったところ、無事本土にたどり着くことができ、感謝してこの石塔を建立したといい、この話から、「航海記念塔」とも呼ばれています。また別の説では、鎌倉3代将軍源実朝(さねとも)の頃、中国に渡ろうとした大船が転覆し大勢が溺死したり、有力御家人・和田一族が滅ぼされ、実朝暗殺後には承久の乱が起き、多くの武士が命を落としたことを受け、その魂を弔うため、貞応年間(1222~1224)にこの塔を築いたとの説もあり、さらには石清水八幡宮を創始した行教の墓という説もあります。江戸時代より前には忌明塔と呼ばれ、亡き父母の四十九日を終えるとこの塔に参り、喪の穢れを清めたと伝わっています。