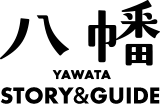松花堂及び書院庭園〈名勝・平成26年10月6日指定〉 松花堂およびその跡〈史跡・昭和32年 7月 1日指定〉
 名勝庭園
名勝庭園
松花堂庭園の内園は、江戸時代のはじめ、石清水八幡宮寺の社僧であった松花堂昭乗が隠居後に住んだ泉坊内の草庵松花堂と書院の一部、そして4~5世紀の古墳である東車塚古墳を改修した庭で構成され、それらが巧みに融合し、大変美しい庭園となっています。現在の内園は、国の名勝に指定されています。
松花堂昭乗(しょうかどうしょうじょう)(1584~1639)は、僧侶としてだけでなく、当代一流の茶道家であり芸術家としても知られ、近衛信伊(このえのぶただ)、本阿弥光悦(ほんあみこうえつ)と並んで「寛永の三筆」といわれています。松花堂とは、松の花が千年に一度しか咲かないと考えられていたことから、大変珍しく美しい出来事の比喩として用いられ、昭乗が雅号としたものです。
昭乗は子どもの頃、八幡に来て仏門に入り、のちに、石清水八幡宮寺を構成していた数多くの僧坊のひとつであった瀧本坊の住職を務めました。昭乗の交友範囲は広く、公家・大名や芸術家等に及び、これらの同時代の文化人を集めて茶の湯を楽しんでいました。50代半ばに近隣の泉坊に隠棲し、寛永14年(1637)に方1丈(3メートル四方)の小さな草庵を建て、それを松花堂と名付けました。この建物は住居と茶室を兼ね、昭乗はここに人を招き、茶でもてなすなど文化的な交流を続けました。
19世紀末期に明治政府が誕生すると、神仏分離令が出され、石清水八幡宮の境内にあった仏教施設とともに、泉坊内の草庵松花堂と書院も解体されました。その後八幡の町の中で何度か移築を繰り返し、最終的に東車塚古墳上の現在地に落ち着きます。この草庵と草庵の庭(露地(ろじ))は、男山山腹の元の所在地と共に、国の史跡となっています。