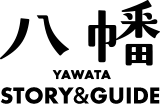草庵 松花堂〈京都府指定文化財・寛永14年(1637) 昭和59年4月14日指定〉

石清水八幡宮の社僧であった松花堂昭乗(1584〜1639)が、瀧本坊の住職を引退した寛永14年(1637)、近くの泉坊に隠居後の住居として建てた草庵です。昭乗は名物の茶道具や茶に必要な道具を泉坊へ持っていき、隠居後も泉坊で公家や大名など交友のあった文化人らを招いて茶を楽しんでいたと推測されます。
屋根は宝形造の茅葺で頂部に瓦製の宝珠を載せ、南側の正面入口には桟唐戸(さんからと)が吊られ、その外観は仏堂のような印象があります。内部は二畳の間を主体とし、土間と勝手が付いています。磚(せん)敷きの土間には竈(くど)が造られ、勝手には置水屋が設えられています。二畳の間の北面は、中央に柱を立て、右に床(とこ)の間、左に3段の袋棚を作っており、一番下の板戸を開けると左に丸炉(がんろ)が設置され、右に小さな棚が吊られています。西面には仏壇が造られています。折り上げの天井の中央部は明治の移設時に新調されたもので、藤(とう)を網代に組み、日輪と鳳凰が極彩色で書かれています。
わずか畳二枚分という空間に様々の要素が複雑に組み合わされており、住居としても茶室としても、禅の境地に通じるように一切の無駄をそぎ落としながら、必要な施設を設けています。昭乗の精神的、芸術的生活の総まとめとして彼の人間性そのものを象徴するような遺構です。
草庵松花堂と草庵の庭(露地(ろじ))は国の史跡となっており、草庵の建物は京都府指定文化財に指定されています。