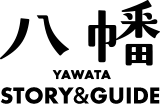泉坊 書院〈京都府登録文化財・江戸前期 昭和59年4月14日指定〉

石清水八幡宮の僧坊のひとつ・泉坊から草庵松花堂とともに移築された書院を組み込んで構成された建築で、明治31年(1898)に上棟された後、大正期にかけて西側部分が増改築されていますが、玄関から奥へ続く座敷列の構成は明治31年当初からのものです。9畳の「玉座の間」と「上段の間」、その手前8畳の座敷および玄関は、昭和
59
年(1984)に京都府登録文化財となっています。玄関は、豊臣秀吉(1537–1598)によって建てられた伏見城の遺構との伝承があり、棟には福禄寿の文字をあしらった鬼瓦があります。主室「玉座(ぎょくざ)の間」と「上段の間」は、折上格(おりあげごう)天井の本格的な書院造りの座敷で、襖(ふすま)に描かれた水墨山水図は、狩野山雪(1590~1650)が描いたと伝わります。書院の造りから桃山期から江戸初期の様式であり、次の間とともに昭乗の遺構を残しつつ近代に再構成された貴重な建築です。