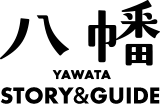茶室「松隠」 (「閑雲軒」)
- 茶室「松隠」
- 茶室の内部
「松隠」は、寒い冬にも緑の葉を保ち、丈夫で耐久性があることから縁起物とされている「松」にちなんで名づけられました。
入母屋造銅板葺の屋根に庇が付き、床を高く張った建築で、均整のとれた穏やかなたたずまいを見せています。
内部は玄関、七畳間に三畳大の相伴席のついた広間、四畳台目の小間、水屋で構成されています。
小間は、石清水八幡宮の境内である男山の山腹の僧坊・瀧本坊にあった有名な茶室「閑雲軒」を再現したものです。瀧本坊の住職であった松花堂昭乗(1584〜1639)が、小堀遠州(1579~1647)と共に作った茶室で、1773年に焼失しましたが、閑雲軒を訪れた茶人らが絵図などの記録を残しており、これらを元に、茶室・数寄屋建築の第一人者である中村昌生(1927~2018)の設計により復元されました。最大の特徴は崖の上に張り出して建てられた懸け造りの茶室である点で、三方に吹放しの縁が回らされ、遠く京の都や伏見・宇治まで見通すことができたといいます。平成22年(2010)に跡地が発掘調査され、見つかった礎石から最大7メートルもの柱で支えられていたことがわかり、「空中茶室」とも呼ばれるようになりました。
そのため、この建物でも床を高く張り、茶室の三方を縁とし、縁に躙(にじ)り口を設けました。内部は床柱に侘びた榁(むろ)の木の手斧(ちょうな)掛けが使われ、床框(とこがまち)は鮮やかな朱色の真塗りで仕上げられています。
天井に開けた突き上げ窓を含め、十もの窓がある構成も、まさに遠州好みの茶室です。