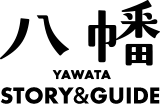茶室「梅隠」
- 茶室「梅隠」
- 茶室の内部
庭園入口から園路沿いに散策すると最初にあらわれる「梅隠」は、千利休の孫にあたり千家の三代目当主として表千家、裏千家、武者小路千家の三千家の基礎を築いた千宗旦(せんのそうたん)(1578~1658)好みの四畳半茶室を再現したものです。
八畳の広間と四畳半の小間で構成され、八畳の広間は西側全体に幅の広い棚を設け、障子を建てています。
四畳半の小間は宗旦の茶の姿がもっとも深く映し出されているといわれ、床は壁・床を土で塗り、床面に紙を貼った「土床」で、床柱には手斧(ちょうな)掛けの跡をそのまま残した栗材を用いるなど、侘びた風情を醸し出しています。茶室の入口は躙(にじ)り口でなく貴人口(きにんぐち)にしており、その代わり外に土間の部分がついていて、そこに潜(もぐ)りが設けられています。露地(ろじ)の中門の形式の一つである中潜りに相当し、それが茶室に結合されている珍しい様式で、古い茶室の形といえます。
松花堂昭乗と同時代に生きた千宗旦は、昭乗や本阿弥光悦(ほんあみこうえつ)などとも親交の深い寛永の文化人でしたが、利休の侘茶を受け継ぎ、修道的で簡素に徹した風を貫いたことで知られています。この茶室は宗旦の茶を理解する上で、又隠(ゆういん)や今日庵(こんにちあん)と並んで貴重なものとなっています。
手水鉢のそばには水琴窟(すいきんくつ)があり、手水鉢から水が滴る際に、地中の壺から反響する涼やかな音色が聞こえます。