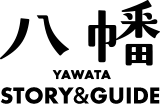松花堂弁当

種類や彩の豊かさで世界にも知られる日本の弁当ですが、代表的な弁当のひとつとしてよく知られている「松花堂弁当」は、四つ切の四角い器(うつわ)に美しく盛り付けられる弁当です。
今から約400年前、石清水八幡宮の社僧で文化人として活躍した松花堂昭乗の愛用の品に、四つ切の塗箱がありました。農家が種入れに使っていた木箱に着想を得て、昭乗が漆塗りの美しい四つ切箱に仕立て、茶道具として用いたといわれています。
この四つ切の塗箱に料理を盛り付け「弁当」としたのは、著名な日本料亭「吉兆」の創業者、湯木貞一氏(1901~1997)です。昭和8年(1933)、八幡市の松花堂で行われた茶会に出席した湯木氏は、部屋の隅に積み上げられた四つ切箱を見て、「料理の器に使えないか」と思いつきました。十字に仕切りがあるその器を見て、異なる料理を入れるという利点に着目し、年月をかけ創意工夫を重ね、食材同士の味や香りが移らず、舌で味わっても、目で味わっても美味しい、機能と美しさを併せ持つ松花堂弁当を生み出しました。湯木氏は、昭乗へ敬意を払って「松花堂弁当」と名付け、日本を代表する弁当スタイルとして全国に広めました。
平成の世になり、京都吉兆 松花堂店が松花堂庭園・美術館の敷地内に開業し、本物の松花堂弁当をその起源である松花堂の地で味わうことができるようになりました。